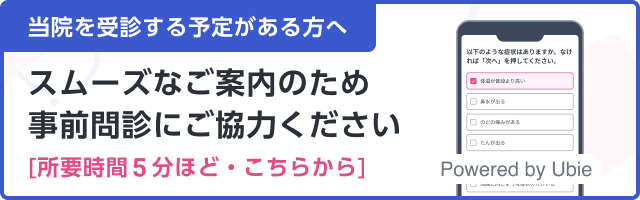当院のリハビリテーション科は“身体機能の最適化”をテーマに、治療から再発予防までを考慮し、患者様に最適な治療を展開します。
リハビリテーション科とは

一口にリハビリテーション(通称:リハビリ)と言いましても、医学的、社会的、職業的などいくつか種類はあります。なお当院は整形外科ですので、当診療科は身体機能の回復・維持を目的とした医学的リハビリテーションの中の運動器リハビリテーションになります。
運動器リハビリテーションとは、医師の診断結果を基にし、(医師の)指示を受けた理学療法士や作業療法士等が患者さまにとって最適とされるプログラムを作成し、日々のリハビリメニューをリハビリ室において行っていきます。当院は、理学療法士が在籍していますので、主に理学療法によるリハビリテーションが中心です。
理学療法によるリハビリテーションの対象となる患者さま(例)
- 手足にしびれがある
- 肩や首に痛みがみられる
- 腕をあげることができない
- 腰痛をなんとかしたい
- 歩くと膝に痛みが出る
- ケガで身体が動かしにくい
- 身体を動かす際に痛みが生じる
- 手術後のリハビリテーション など
理学療法とは
理学療法のリハビリは、運動療法、物理療法、装具療法に分けられますが、基本は運動療法です。これらの訓練や治療を理学療法士(PT)の助けを借りながら行うことで、日常生活に必要とされる、座る、起き上がる、立つ、歩行する、などの基本動作の維持、改善を図っていくという内容になります。
運動療法

主に身体を動かすことが中心となります。具体的には、理学療法士(PT)のサポートを受けながら、関節可動域訓練、筋力増強訓練、持久力訓練、運動協調性訓練、歩行訓練等を行っていくわけですが、これによって廃用症候群(寝たきりによって、関節拘縮、筋力低下、筋委縮等がみられている状態)を予防するというだけでなく、体力の向上や心肺機能の改善などにもつながっていきます。なお運動量や強度については、医師や理学療法士が各々の患者さまの全身の状態をしっかり確認しながら、リハビリメニューを考案していきます。
これらを続けていくことで、筋力アップ、日常動作や関節可動域の改善、持久力の向上が図られるほか、体幹もトレーニングすることで転倒の予防にもなります。また運動をすることは、自然治癒力を高めていくことにもなります。
物理療法
物理的なエネルギーを利用し、その刺激による生体反応によって、患者さまにみられている痛みやしびれ、むくみなどの症状を和らげていく、悪化している血流を改善させていくなどするのが物理療法です。
この物理的エネルギーには、熱、水、電気など様々ありますが、熱であれば患部にホットパックを当てることで血流の改善を図る温熱療法、水であれば水圧の刺激によって筋肉などの凝りを解消していくウォーターマッサージベッド、電気であれば、患部に電気刺激を与えて神経痛等の痛みなどを軽減していく電気療法を行っていきます。このように痛みを軽減させるために用いるほか、筋肉の緊張緩和や関節の動きを改善させる効果もあるので、運動療法をより効果的にするということもあります。
装具療法
日常生活において大事な動作である歩くという行為が、痛みやケガ、麻痺などによって難しいとなった場合は、装具で患部を固定するなどして、痛みを軽減、あるいは運動能力を向上させるようにします。これを装具療法と言います。
同療法については、(骨折などの)治療によって一時的に使用する治療用装具のほか、治療を終えて障害が固定した後、身体障害者の方が日常生活を向上させるために使用する更生用装具などがあります。
リハビリテーションの流れ
当院のリハビリテーション科では"姿勢・動作を変化させるのが理学療法士の専門性"という考えのもと、"身体機能の最適化"を通して地域の患者さんの日常生活上で生じる困りごと(関節の痛み、動きづらさ、パフォーマンス低下)の解決を目的にしています。
①問診

医師による診断後、必要性に合わせてリハビリが処方されます。 理学療法士・柔道整復師はこの診断を元に、患者さんの困りごとの内容(痛み:場所・質・大きさ・頻度など)が日常生活のどの場面で生じているか、患者さんとの会話をしながら整理していきます。
②疼痛の検査

①で得たヒントを元に、基本動作(寝返り、起き上がり、座位・立位保持)や歩行、走行、スポーツ動作を確認し、疼痛が生じるタイミングと場所の特定を行います。関節にかかっているストレスと傷んでいる組織を各種整形外科テストで絞り込んでいきます。検査時はなるべく痛みが強くならないように配慮しながら行います。
③疼痛除去テスト

②で得た結果を元に、痛い箇所をどのようにコントロールすれば疼痛が軽減できるかを確認します。関節の痛みは局所の問題だけでなく、他の部位に問題が生じていることも多く、立位姿勢や動作を細かく確認し、患者さんの個別性をしっかりと把握する必要があります。
④治療
今までの過程から得た疼痛の原因を元に解決の優先順位を決定し、治療に入ります。 一回で改善するものから多くの治療が必要なものまでありますので、患者さんが不安にならないよう、医師と治療内容と進行度の共有、患者さんへの内容の説明や最適な負荷量の設定を行なっていきます。 治療には日常生活の過ごし方、運動量のアドバイス、自主トレーニングの指導も行います。
⑤再評価

(④)の結果を振り返り、さらに治療内容に改良、修正を加えます。必要に応じて医師へ治療内容の方向性、画像評価、関節注射等の相談、介入頻度や複数のスタッフでの介入検討、入谷式インソールのご案内をします。